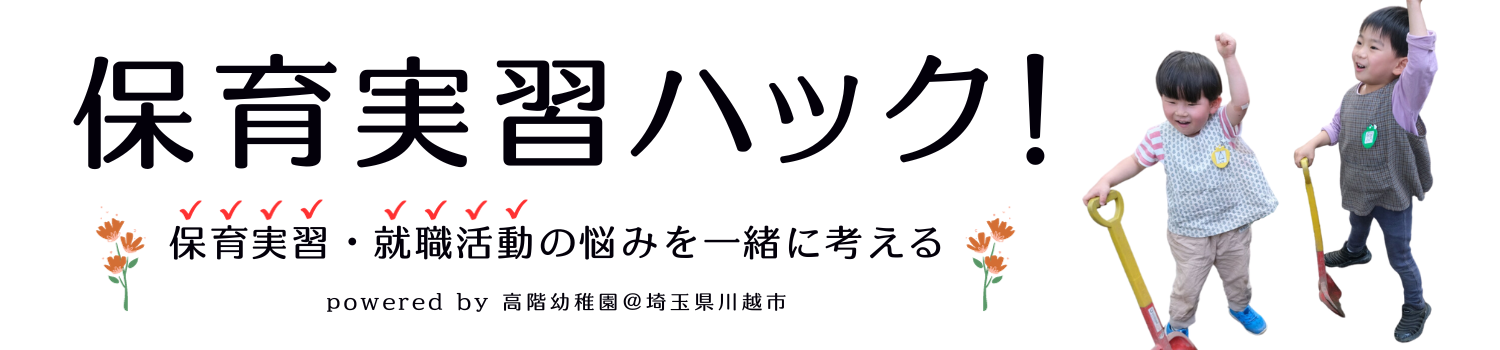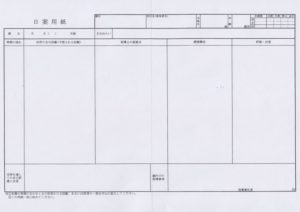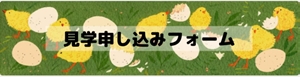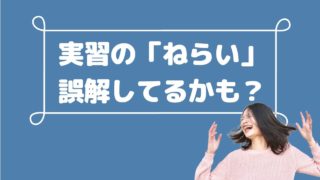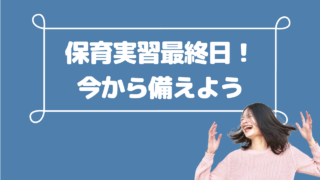今回はその経験を共有します。つまり、「ダメ」な書き方の例を詳しく分析。
これによって、あなたが日誌の書き方で困らないためのポイントをお伝えしたいですね。
保育実習日誌の書き方、「ダメ」な例
実習日誌の書き方には、明確に「これはダメ」な例があります。
「園」の先生の使命は発達の援助。発達に役立たない日誌を書いているヒマはないんですよ。
※当サイトでは「幼稚園・保育園(保育所)・認定こども園」を総称して「園」と呼ぶことがあります。
しかし残念なことに、誤った日誌の書き方が指導されている大学もあるようです。私の受けた講義がまさにそれ。
「日案」用紙を使って実習日誌の練習をした時のことです。
確か5歳児の保育を想定していたと思いますが、「その日に何をするか」を最初に決めてしまうんですよ。
『幼稚園教育要領』にも明記されています。
幼児の主体的な活動が確保されるよう幼児一人一人の行動の理解と予想に基づき,計画的に環境を構成しなければならない
「一人一人の行動の理解と予想」に基づいていたら、「20人全員でレストランごっこをする」なんて書けるわけないんです。
「5歳児20人全員が心の底から同じ遊びをしたがっている」状況は、「20人が心の底から同じものを食べたがっている」のと同じくらいありえない、と考えるとわかりやすいですね。
では、保育日誌の正しい書き方は?
まずは「発達」を掘り下げてみます。
発達の流れをつかむと「子供がどのように心を動かしたがっているか」がわかりま、それでようやく「子供に合った日誌の書き方」ができるんです。
※ここでは「発達=心理的発達」として話を進めます。
※個体差・環境差があるため、年齢はあくまで目安です。
子供自身が「安心」・「意欲」・「目的力」を大きくしていけるように関わりを持つ、そのためできることを考えておく、
もちろん、発達の知識をベースとして一人ひとりに「オーダーメイド」に対応する必要があります。
自分の知識に子供の生活を当てはめてしまうと、発達を妨げることにもなりますので、注意しなければなりません。
こちらの記事↓も参考にしてください。
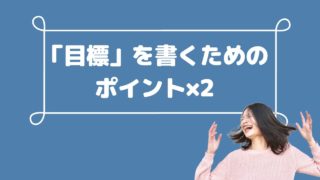
実習日誌(特に日案)の書き方:まとめ
書き方がわかったからといって実習日誌がスラスラかけるわけでもありませんが、今回の内容を押さえてもらえれば書き方で悩む回数は格段に減るはずです。
また、 ①~③を押さえて書けるようになると、保育で見るべきポイントがわかり、保育がスムーズになるでしょう。